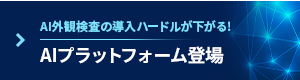ネットワークからクラウド、セキュリティ、モバイル、システムインテグレーションまで幅広く事業を展開し、多種多様なITサービス・ソリューションで社会インフラ基盤を支えてきた株式会社インターネットイニシアティブ(以下、IIJ)。同社が膨大なサービス群を安定稼働させるためのインフラ基盤として構築・運用している「Next Host Network」(以下、NHN)は2008年10月より提供を開始。市場の変化やサービスの拡大に合わせて強化を重ね、現在は9,000台以上のサーバーで構成される大規模サービス基盤へと進化を遂げている。
NHNのサーバー群には、開発当初からインテル® Xeon® プロセッサーが使われており、2023年の新サーバー選定においても、第4世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを採用。同社では、CPUでの推論パフォーマンスを向上させる新しい拡張命令セット「インテル® AMX」が同プロセッサーに搭載されていることに着目し、GPUを用いらずにCPUで推論を行う生成AI活用の取り組みを開始している。
本稿では、NHNの運用、及び今回の生成AI活用に携わっているIIJ 基盤エンジニアリング本部 基盤技術部 システム基盤技術課 課長代行 早田 祥弘 氏に話を伺い、同社のサービス基盤と生成AIの活用において、インテル® Xeon® プロセッサーが担う役割を紐解いていく。
第4世代 インテル® Xeon® プロセッサーに実装された「インテル® AMX」が
“GPUいらず”の生成AI開発の鍵に?
IIJが提供する膨大なITサービス・ソリューションは、サービスの運用効率向上とコスト圧縮を目的に開発されたサービス基盤インフラ「NHN」上で稼働している。まさに同社のビジネスを支える根幹であるNHNだが、その分、運用チームにかかる負荷は大きく、基盤運用業務の効率化は喫緊の課題となっていた。NHNの構築・運用を担当しているシステム基盤技術課の早田氏は次のように語る。
「IIJが展開するサービスは多岐にわたり、その基盤であるNHNに対するニーズも多種多様です。サービス自体が日々進化し続けていることもあり、毎日何かしらの調整を行っているような状況でした。ITサービスはスピード感が重要になりますので、「いつまでに作業を終わらせてほしい」という要求も多く、優先順位付けとスケジュール管理の部分に課題を感じていました」(早田氏)
適切かつスピーディなサービス基盤運用を実現するためには、サービスを提供している事業部とのコミュニケーションを密にする必要があったと早田氏。しかし、限られたメンバーで24時間365日対応していくことは困難だったと課題を口にし、近年のビジネストレンドといえる「生成AI」の活用に着目したと話を続ける。
「当時は、生成AIのビジネス活用に取り組む企業も多く、AIブームが起きていた時期でしたが、そのほとんどがGPU(グラフィックボード)の利用を前提としたもので、IT基盤の運用を行っている立場からはリスクも大きいと感じていました。NHN自体が、さまざまなニーズに対応するための「汎用性」を重視しており、それがCPUにインテル® Xeon® プロセッサーを採用してきた理由の1つにもなっています。そのNHNの運用を効率化する手法として、調達性や互換性、さらにコスト面でも不安が残るGPUを前提としたアプローチは採用しづらく、CPUで推論処理を行えないかという観点で検討を開始しました」(早田氏)
互換性(汎用性)とパフォーマンス(性能)の観点からインテル® Xeon® プロセッサーを採用してきたNHNでは、2023年の新サーバー選定にあたっても、第4世代 インテル® Xeon® プロセッサーを採用している。早田氏は、このインテル® Xeon® プロセッサーに搭載されている拡張命令セット「Intel® AMX」に注目し、GPUを用いらずにCPUで推論処理を行うチャットボットの開発をスタートさせた。
「利用者からの“より強い計算リソースを”という要望に対応したサーバーメニューを開発するため、インテル® AMXが実装された第4世代 インテル® Xeon® プロセッサーを採用したという背景もあり、NHNの運用効率化にあたってもインテル® AMXの活用を第一に考えました。具体的には、社内システムに書き込まれたNHNへのリクエストをAIが解析し、必要な情報を抽出してチャットに流すという仕組みを構築することで人的ミスを減らし、読み落とし・対応遅れの抑制を図っています」(早田氏)
量子化技術で計算量を削減し、CPU推論のパフォーマンスを担保
こうしてインテル® AMXの活用により、CPUで推論を行うチャットボットサービスの開発に着手した早田氏は、「Intel® Extension for PyTorch」というライブラリを用いて推論性能を調査。小規模言語モデル(SLM)の「Phi-4」や、大規模言語モデルの「Llama」などを用いて検証を重ね、高いリアルタイム性を必要としないチャットボット用途では十分な推論速度が得られることを確認した。
「AI関連の技術は日々進化を続けており、計算量を減らす量子化技術も実用化されてきています。今回の取り組みでも、インテル® AMXを使った量子化技術が出てきたことで、文章を生成する速度が大幅に向上しました。当初は1つの文章を生成するのに5~6分かかっていたのですが、現在は1分以内で作れるようになっています」と早田氏。
GPUの推論処理速度と比較すると多少の差異はあるものの、リアルタイムのAIチャットなどでなければ問題ないパフォーマンスを得られていると手応えを口にする。
またインテル® AMXの活用にあたっては、インターネットのコミュニティなどから情報を収集しながら、ほぼ独学で進められたそうだ。早田氏は「試行錯誤を続けるなかで、コミュニティ内のプロジェクトにコミットしているインテルのエンジニアから提供された最新情報や、ナレッジには助けられました」とインテルからの間接的なサポートに言及する。
こうして、GPUを使わないチャットボットサービスの稼働が開始された。現在はPoC段階だが、すでに実際の業務で使われており、想定どおりの効果が得られているという。
「これまで人が文章を読んで判断していた業務が、AIの自動分析で問題点を抽出・提示する仕組みを導入することで大幅に効率化できました。ミッションクリティカルなサービスが稼働しているNHNの運用では、週末や深夜に対応が必要になるケースも当然あり、そういった人手が不足する時間帯でもAIがしっかりと問題点に気付き、必要な情報を教えてくれるのは非常に大きな効果といえます。管理職の立場から見ても、簡潔な文章で情報を把握できるようになり、大変助かっています」(早田氏)
ただ、推論速度が向上した結果、運用チームに膨大な量の通知が届くようになり、運用負荷の軽減という意味では完全に課題を払拭できたわけではないとし、早田氏は「今後は運用する“人”と“機械(AI)”のバランスを考えながら、改良を進めていきたい」と力を込める。
「今回の取り組みもそうですが、AI活用では定量的な効果を測定しづらいケースが少なくありません。ただし、今後もAI活用を促進していくことを考えれば、統計的に調べるための手段を確保する必要があり、サービスの開発と併行して取り組みを進めているところです」(早田氏)
生成AI活用における選択肢の幅を広げるため、IIJの挑戦は続く
今回の取り組みを踏まえ、IIJでは今後も幅広い領域で生成AIの効果的な活用に取り組んでいくという。NHNの運用をはじめとする社内業務への適用はもちろん、事業部門においてもAI活用の気運が高まっており、NHNに対する要望も増えてきているという。そのなかで、インテル® Xeon® プロセッサーとインテル® AMXによるCPU推論のポテンシャルを明確化したチャットボットサービスは、事業部門のAI活用における選択肢を増やすという効果も生み出している。
「提供中のサービスをAIで強化したいので、高性能なGPUを入れてほしいといったリクエストも増えてきていますが、今回の開発で、インテル® Xeon® プロセッサーでもこれだけの推論処理が可能ですと提案できるようになりました。実際、当社の社員が自由に記事をアップできるサイトで今回の成果を公開したところ、かなり反響が大きく、AI活用は必ずしもGPUありきではないということが認知されてきたように感じています」(早田氏)
同社では、GPUを用いたAI活用も含め、さまざまな選択肢を提供できるようNHNの整備を進めて行く予定だ。そのなかで、AIの推論処理を始め、多様なワークロードに対応するインテル® Xeon® プロセッサーの有用性は高まっていくと早田氏。第6世代のインテル Xeon プロセッサーである「Granite Rapids」の導入も視野に入れ、生成AIの業務活用に向けた活動を続けていきたいと今後の展望を語る。
「AIは、チャットだけでなくいろんな形で我々を支えるひとつの手段として利用されていくものと捉えています。もちろん、IIJが提供するサービス・ソリューションにおいてもAIの活用は不可欠になっていくはずで、その意味では、さまざまなプラットフォームで運用できる知見を蓄積することが大切になります。冒頭で話したように、我々が運用しているサービス基盤は、汎用性と性能を重視して構築しており、AI活用においても1つの技術に依存することなく、ニーズに合わせて最適な機材の提供を目指して検証を進めていきたいと考えています」(早田氏)
AI活用にはGPUが不可欠という固定観念を打ち破り、インテル® Xeon® プロセッサーの拡張命令セットを用いたCPU推論の可能性を切り開いたIIJの取り組みは、生成AIによる業務効率化やイノベーションの創出を目指す企業・組織にとって重要な“気づき”を与えてくれるはずだ。
※取材内容は2025年3月時点での情報です。